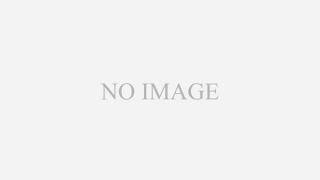「デザインに時間をかけすぎてコーディングに進めない…」
そんな悩みを解消するためのワイヤーフレーム設計。
Figmaを使えば、全員が同じ土台を共有しつつ、直感的に画面設計ができます。
本記事では、
- なぜワイヤーフレームが重要か
- Figmaの基本操作とおすすめ設定
- Step by Stepで進める具体的手順
- 完成後のチェック&チーム共有術
まで完全網羅。今日から使える**「Figma ワイヤーフレーム 作成 方法」**をマスターしましょう!
1. なぜワイヤーフレームが必要なのか?メリット3選
- 設計の見える化
- ページ構成や導線を一目で把握。認識齟齬を防止します。
- 開発スピードの向上
- ビジュアルデザイン前に機能・情報設計を固め、作り直しを減らせます。
- チーム共有とフィードバック
- デザイナー・エンジニア・クライアント間で「何を作るか」を確実に合意形成。
2. Figmaの初期設定:最適なワークスペースを用意する
- ブラウザ版 or デスクトップ版 → チームならデスクトップ版を推奨
- ファイル命名ルール
ProjectName_wireframe_YYYYMMDD- ページ分け:Home/InnerPage/Form など用途別にタブを用意
3. Step by Step:Figmaでワイヤーフレームを作る手順
Step1:フレーム(アートボード)の作成とグリッド設定
- Frame Tool (F) を選択し、デバイスプリセット(Desktop 1440px など)を配置
- 右パネルの Layout Grid → + → Columns を設定(12カラム・ガター24px が定番)
- グリッドの不透明度を下げて、設計ガイドとして活用
Step2:コンテンツブロックの配置
- 四角形ツール (R) でヘッダー/メインビジュアル/カードなどを大まかに配置
- テキストツール (T) で「見出しH1」「見出しH2」「本文テキスト」を仮置き
- 色はグレー系、背景透過でプレースホルダーと識別しやすく
Step3:コンポーネント化で再利用性アップ
- 共通パーツ(ナビゲーション、ボタン、カード)を選択
- 右クリック → Create Component
- Assetsパネルからドラッグ&ドロップで複数画面に適用
- インスタンス化したコンポーネントはマスターで一括更新
Step4:オートレイアウトで柔軟な調整を
- コンポーネントやグループに Auto Layout を適用
- パディング・間隔を数値で指定し、要素追加/削除時も自動調整
- レスポンシブ設計のベースとしても有効
Step5:プロトタイピングで画面遷移をシミュレーション
- Prototypeタブ を開き、要素から矢印をドラッグ
- 遷移先フレームを指定し、Animation は「Instant」または「Smart Animate」
- プレビュー(▶︎)で動作確認し、関係者にURL共有
4. 完成後のチェックリスト
- フレーム毎の命名規則が統一されている
- コンポーネントにAuto Layoutが適用済み
- テキスト階層(H1→H2→H3)が設計に反映されている
- プロトタイプ遷移がすべて動作する
5. チーム共有とフィードバックのコツ
- コメント機能を活用し、要素単位でフィードバック
- バージョン履歴をこまめに保存し、変更を追跡
- SlackやNotionと連携し、フィードバック期限を明示
まとめ:これであなたもFigmaワイヤーフレームの達人!
- 設計段階での可視化 が品質と効率を両立
- Auto Layout+コンポーネント で再利用性&保守性アップ
- プロトタイプ共有 による迅速な合意形成
まずは本記事のStep1~Step5を順に実践し、
「Figma ワイヤーフレーム 作成 方法」を体感してみてください。
(Visited 111 times, 1 visits today)