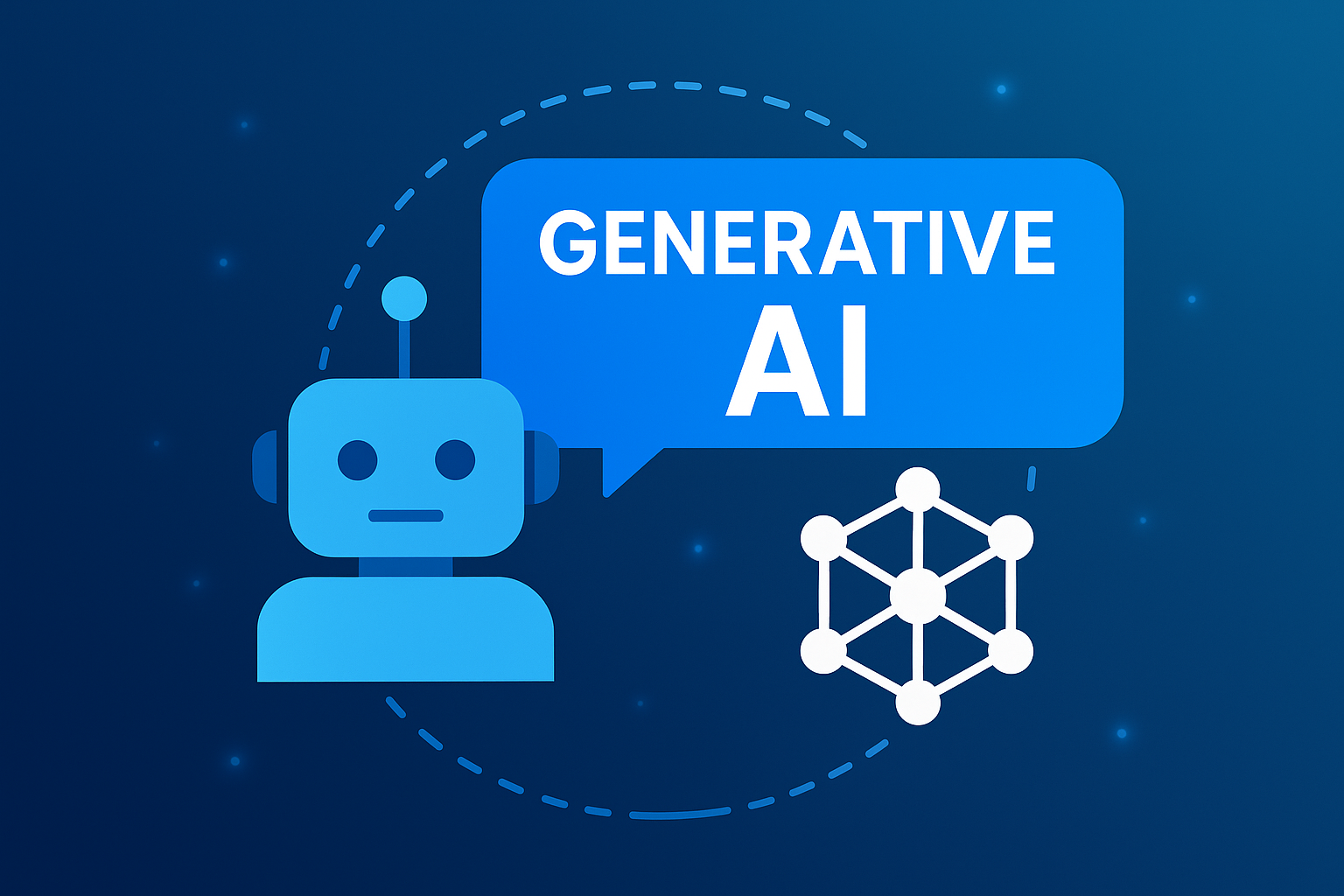はじめに:テーマ選びで失敗する人が多すぎる
WordPressの構築相談を受けていると、
- 「とりあえず有名だからこのテーマにしました」
- 「無料テーマで始めたけどカスタマイズ地獄です」
- 「デザインは良いけどコードが重すぎてスコアが悲惨です」
という声に本当によく出会います。
テーマ選びは「見た目の好み」ではなく、
運用コスト・パフォーマンス・拡張性・セキュリティ・ビジネス要件まで含めた技術選定です。
この記事では、
- 無料テーマと有料テーマの本質的な違い
- テーマ選定時に必ず見るべきチェックポイント
- フロントエンドエンジニア目線で確認すべきコードと機能
- 実務で「やってはいけないテーマの選び方」
- 学習者がテーマでスキルアップするための視点
までを、WordPress本体や公式ディレクトリのルールに基づきつつ整理します。
フロントエンドを勉強中の方も、実務で案件を回している方も、
「この基準で選べば大怪我しない」という軸を持てる内容にしているので、そのまま案件・自社サイトにも使ってください。
WordPressテーマの前提知識:まずはここを押さえる
テーマは「見た目」+「構造」+「機能の束」
WordPressテーマは以下を一式で提供します。
- レイアウト(ヘッダー、フッター、サイドバー、シングル、アーカイブなど)
- タイポグラフィ、配色、余白設計
- ブロックエディタ対応(ブロックパターン、スタイル、theme.json)
- ウィジェット・メニュー・カスタマイザー・サイトエディタ対応
- 追加機能(CTA、LPテンプレ、スライダー、カスタム投稿タイプ等)
ここで重要なのが、
「テーマは“なんでも入りパッケージ”なので、選び方を間違えると後から身動きが取れなくなる」
という点です。
無料テーマと有料テーマの違い:価格以外に何が違うのか
1. ライセンスと信頼性
公式ディレクトリの無料テーマは、WordPress.orgのガイドラインに基づいて審査されており、
100% GPL互換であること、基本的なセキュリティ要件やテーマ構造を満たしていることが前提です。
一方、有料テーマは:
- テーマショップやマーケットプレイス(ThemeForestなど)で販売
- ライセンス形態がまちまち(ただし近年はGPL準拠が主流)
- コード品質・サポート品質は販売元次第
ポイント
- ビジネス利用なら「GPL互換」「信頼できる販売元か」を必ず確認。
- ライセンスが不透明なテーマは選ばない。
2. デザインと用途特化度
無料テーマ:
- 汎用的なデザインが多く、追加のCSSやブロックで作り込む前提。
- 「シンプルで軽量」が武器のことが多い。
有料テーマ:
- コーポレート、ブログ、メディア、EC、サロン、採用サイトなど「用途特化型」が多い。
- 世界観が作り込まれており、そのまま使っても見栄えしやすい。
- 日本向けテーマ(例:国産テーマショップ各社)は日本語レイアウト・縦書き風・余白感などが実務レベルで整っていることが多い。
デザインに時間をかけたくない実務案件では、有料テーマの「最初から整っている強さ」はかなり大きいです。
3. 機能の充実度と「盛りすぎリスク」
無料テーマ:
- 必要最低限+ブロックエディタ対応。
- 不足分はプラグインで補う構成になりやすい。
有料テーマ:
- LPテンプレ、ヘッダーバリエーション、多彩なブログレイアウト、 広告枠、ランキング、会員機能、CTA、スライダー、アイコンフォントなどを「全部載せ」しているものも多い。
ここでの落とし穴:
- 不要な機能が大量に読み込まれ、ページ速度が低下
- jQuery依存+レガシーコード多めで、コアアップデートとの相性が悪くなる
- GutenbergやFSEと思想が噛み合わず、「独自ショートコードまみれ」になる
フロントエンドエンジニアとしては、
「機能が多い=良いテーマ」ではなく
「必要な機能だけ、適切な実装で提供しているテーマ」を評価すべきです。
4. サポート・アップデート
無料テーマ:
- フォーラムベース、作者の善意頼り。
- 放置されることもあるので、最終更新日や対応バージョンを必ず確認。
有料テーマ:
- 多くは一定期間のメールサポート、マニュアル、FAQを提供。
- 大手ショップはWordPress本体のアップデートに追従してくれる傾向が強い。
商用案件で「アップデートに追従しないテーマ」を選ぶのはほぼ自爆行為です。
5. トータルコスト
無料テーマは「初期費用ゼロ」ですが、
- カスタマイズに工数がかかる
- デザイン調整にデザイナー/コーダー時間が必要
- 不具合対応の調査コストが発生
結果的に、工数単価で見れば有料テーマの方が安くつくケースは多いです。
実務&学習者向け:テーマ選定チェックリスト
ここからは、実際に案件を回すフロントエンドエンジニアの視点で
「この条件を満たしているか」をテーマ選びの軸として整理します。
1. コード品質
最低限チェックしたいポイント:
- 余計なインラインスタイル乱発になっていないか
- テンプレート階層に沿った構造になっているか
- functions.php に無駄な処理やベタ書きオプションが積み上がっていないか
- CSSが肥大化しすぎていないか(汎用クラス設計か、無限に似たセレクタが並んでいないか)
- 最新のWordPress機能(ブロックエディタ、theme.jsonなど)への対応状況
開発者ドキュメント、デモサイトのマークアップを見れば「設計思想」はかなり読めます。
2. パフォーマンス
- 不要なスライダーJSやアイコンフォントを全ページで読み込んでいないか
- 画像の遅延読み込みや適切なサイズ指定がされているか
- Core Web Vitals を著しく損なう仕組み(巨大ヒーロースライダー、重いアニメーション等)がデフォルトになっていないか
実務では、テーマ導入前にデモサイトをLighthouseで計測しましょう。
3. 拡張性・カスタマイズ性
- 子テーマ運用を前提とした構造か(フック・テンプレ分割・上書きしやすさ)
- 独自ショートコード依存が強すぎないか
- 将来、別テーマに乗り換えるときの「撤退コスト」が高すぎないか
「そのテーマをやめた瞬間、ページがショートコードの墓場になる」テーマは避けたいところです。
4. ブロックエディタ・FSE対応状況
- ブロックパターン、スタイルバリエーションが素直に使えるか
- サイトエディタと従来テーマ機能が中途半端に競合していないか
- 編集画面が重すぎて運用担当が嫌になる未来が見えないか
これからの案件では「ブロック前提で自然に組めるテーマ」を選ぶ方が長生きします。
5. サポート・情報量
- 日本語ドキュメントがあるか
- 不具合事例や実装Tipsが検索すると大量に出てくるか
- 開発が止まっていないか(更新履歴・お知らせを確認)
「情報が少ないテーマ」は、トラブル時に全部自力調査になるので学習用途以外では非推奨です。
無料テーマを選ぶべきケースと戦い方
無料テーマが向いているケース
- 学習者としてテーマ構造やブロックエディタを理解したい
- 小規模な個人ブログや検証環境
- 要件がシンプルで、余白とタイポを自分で整えられる
この場合に意識したいポイント:
- 公式ディレクトリから選ぶ → GPL互換・最低限の審査を通過しているため安心感がある。
- メジャーで更新が継続しているテーマを選ぶ
- 子テーマを作ってCSS・テンプレートを触る
- 「無料テーマ+自作ブロック・SCSS」で、フロントエンドスキルを鍛える教材として使う
無料テーマ利用時の注意点
- 広告や追跡コードが仕込まれていないか確認
- 特定リンクの削除が制限されていないか
- カスタマイザー/独自オプションが中途半端にロックされ、有料版誘導が強すぎないか
有料テーマを選ぶべきケースと見極め方
有料テーマが向いているケース
- クライアントワーク(企業サイト、店舗サイト、メディア)
- デザインや世界観を短納期で形にしたい
- マーケ施策(LP量産、ブログ運用、CV導線)まで考えたい
- サポートやドキュメントが必須
有料テーマ選定で見るべきポイント
- 目的特化と汎用性のバランス
- コーポレートなのに装飾過多で読みにくいテーマは避ける
- ブログなのに見出し設計が弱いものも避ける
- 将来、機能追加しても破綻しない設計かを見る
- デモサイトの質と再現性
- デモで表示しているデザインが、テーマ同梱機能だけで再現可能か
- 画像やコンテンツを差し替えた時でも破綻しないか
- Update実績とサポート体制
- 最終更新日
- WordPress最新版対応状況
- サポートへの導線(フォーラム、チケット、マニュアル)
- コードへの配慮
- 意味論的なHTMLか
- 不要なscriptの多重読み込みがないか
- ブロックエディタとの整合性
ここまでチェックして「これは案件で使える」と判断できるテーマだけを採用候補にすべきです。
実務でやりがちなNGなテーマ選び
NG1:デザインだけで即決する
- スクロールアニメーションてんこ盛り
- ヒーロースライダー4段重ね
- 全面動画背景
こういうテーマは、計測するとLCP・CLSが壊滅していることが多く、
SEO・広告・CVの観点から実務ではマイナスになることも。
NG2:独自ビルダー依存のテーマにハマる
ページビルダー専用テーマで、
- 独自ショートコード
- 独自ウィジェット
- 独自エディタUI
にロックインされると、移行コストが爆発します。
Gutenbergや標準ブロックをベースに拡張しているテーマの方が長期的に安全です。
NG3:購入先・制作者を調べない
- 開発者情報がない
- 会社住所・連絡先が不明
- デモも雑、マニュアルも貧弱
この時点で候補から外して良いです。
フロントエンドエンジニア視点:テーマで腕を磨く具体的な着眼点
学習者・実務者向けに、テーマ選びとセットで意識してほしいポイントです。
1. テンプレート階層とブロックテーマ構造を読む
- header.php, footer.php, single.php, archive.php の構造
- ブロックテーマなら templates/ parts/ theme.json の関係
- どこでループを書き、どこでコンポーネント化しているか
これはテーマを「読む」ことで一番学べる部分です。
2. 子テーマ運用を前提にする
- functions.php の追加
- 上書きテンプレートのパターン
- 独自CSS設計(BEM風、ユーティリティ、レイアウトクラス等)
「親テーマを直接いじらない」が実務の大前提です。
3. JavaScriptの書き方を見る
- イベントの扱い(DOMContentLoaded, load, scroll)
- ライブラリ依存状況(jQueryのみ前提は古いことが多い)
- 不要なグローバル変数やネームスペース汚染
テーマのJSは、その制作者の思想が最も露骨に出る部分です。
4. アクセシビリティとセマンティクス
- h1 がページごとに適切に設定されているか
- nav, main, footer, section, article などの使い方
- コントラスト比、フォーカスインジケータ、ARIA属性
ここをきちんとしているテーマは、総じて信用できます。
テーマ選びの実践フロー(案件・自サイト共通)
- 要件定義を書く
- サイト種別(コーポレート、オウンドメディア、EC、採用)
- 必要な機能(LP、ブログ、検索、カスタム投稿、会員制等)
- 想定運用担当者のスキル
- 無料/有料を問わず候補を3〜5個に絞る
- デモサイトのデザイン
- 日本語対応
- 更新履歴
- 技術チェック
- デモサイトのHTML/CSS/JS
- Lighthouse計測
- 管理画面UIやブロックエディタの挙動
- 撤退戦略を考える
- 将来別テーマに移行する際、コンテンツ資産が壊れないか
- 固有ショートコードや専用ブロックに依存しすぎていないか
- 最終決定
- 工数、ライセンス、サポート体制を含めて総合判断
このフローを習慣化すれば、「なんとなく有名だから」で選んで詰むパターンはかなり減らせます。
まとめ:無料か有料かではなく、「戦略と構造」で選ぶ
- 無料テーマは
- 学習用、検証用、小規模サイトに最適
- 公式ディレクトリから選び、子テーマで育てる
- 有料テーマは
- ビジネス・クライアント案件で強い
- デザイン・機能・サポートを時間コスト込みで評価する
- フロントエンドエンジニアにとってテーマは
- 「完成品」ではなく「ベースフレーム」
- 読み解き方・選び方を理解すれば、案件の品質とスピードが大きく向上する
テーマは安易に選ばず、「要件 → 技術 →運用 → 撤退」まで含めた設計で選びましょう。
関連して知っておくと武器になるポイント集
最後に、この記事とセットで押さえておくと、現場でかなり有利になるトピックを挙げておきます。
1. プラグインとの責任分担
- テーマは「見た目とレイアウト」中心
- 問い合わせフォーム、SEO、キャッシュ、セキュリティなどはプラグイン側に任せる
- テーマに依存した機能が多いほどロックインが強くなるので注意
2. ブロックテーマ時代の設計
- theme.json によるスタイル・余白・カラー統一
- 独自ブロック vs コアブロック活用の設計バランス
- 既存PHPテーマからブロック化する時の考え方
3. Core Web Vitals 最適化
- 不要スクリプトの読み込み制御(wp_dequeue_script 等)
- 画像最適化(srcset, sizes, WebP, 遅延読み込み)
- ヒーローエリアの作り方とLCP改善
4. マルチデバイス・アクセシビリティ
- スマホファーストで余白とフォントサイズ設計
- キーボード操作、スクリーンリーダー対応
- 色覚多様性への配慮
5. テーマを教材にして「読む習慣」をつける
おすすめの学び方:
- 気になったテーマをローカルに入れて、テンプレートとCSSを読む
- なぜこのクラス設計なのか、自分ならどう書くかを考える
- 子テーマで少しずつ改良してみる
このプロセス自体が、実務に直結する最高のトレーニングになります。